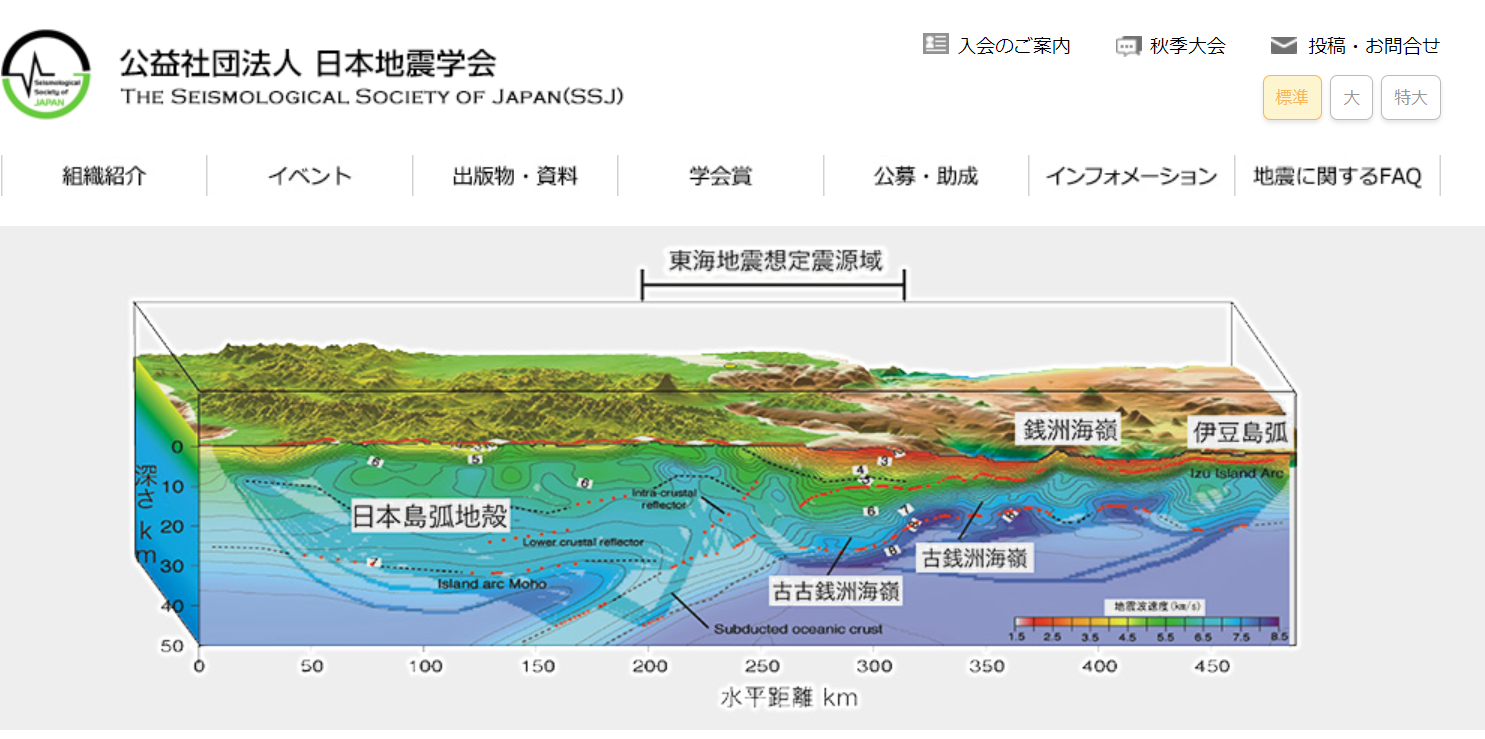1880年(明治13年)2月22日、横浜でマグニチュード5.5~6.0の地震が発生しました。被害は比較的小規模で、煙突の破損や家屋の壁が崩れる程度でしたが、この地震は当時の日本社会、特に外国人居住者に強い印象を与えました。これを契機に、日本で初めての地震学会が設立され、地震観測や耐震建築の研究が本格的に進められることになりました。
地震学会誕生のきっかけ
1880年(明治13年)2月22日 横浜地震
マグニチュード5.5~6.0程度と推定される横浜地震が発生しました。
日本地震学会発足の契機
被害としては横浜で煙突の破損が多かったことと、家屋の壁が落ちた程度でしたが、当時は明治になって十年と少し経ち、この地震を体感した外国人らを中心に強い衝撃を与え、これを契機に日本地震学会が発足し、地震の観測や耐震・免震建築などの研究が精力的に進められました。全国的な地震学会の発足は、1911年(明治44年)アメリカの地震学会に比べ30年以上早い発足でした。
公益社団法人日本地震学会
目的と事業
公益社団法人日本地震学会は、地震学に関する学理及びその応用についての研究発表、知識の交換、及び内外の関連学会との連携を行うことにより、地震学の進歩・普及を図り、もってわが国の学術の発展に寄与することを目的としています。
これらの目的を達成するために、地震学に関する次の事業を行っています。
出典 公益社団法人日本地震学会
まとめにかえて
横浜地震は地震学会発足のきっかけとなりました。
公益社団法人日本地震学会は、地震学に関する学理及びその応用についての研究発表、知識の交換、及び内外の関連学会との連携を行うことにより、地震学の進歩・普及を図り、もってわが国の学術の発展に寄与することを目的としています。
出典 日本地震学会の概要 目的と事業
この地震では大きな火災等もなく被害は少なくようでしたが、学会を発足させ日本の地震学の進歩・普及を図ろうととの取り組みが必要だと当時の人たちの決意が想像されます。