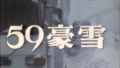1586年1月18日、戦国時代の日本列島を震撼させた天正地震は、マグニチュード8.6と推定される巨大地震でした。この地震は岐阜県を中心に甚大な被害をもたらし、帰雲城の消滅や戦国大名の運命を大きく左右しました。一方で、この災害を経て復興に取り組む人々の姿は、歴史を越え、現代の私たちに大切な教訓を伝えています。本記事では、天正地震が歴史や政治、そして地域社会に与えた影響を振り返り、その復興の知恵について考えます。
マグニチュード8.6程度の地震の規模
1586年1月18日(天正13年11月29日) 天正地震

天正地震と歴史
地震に消えた城
岐阜県白川郷のほぼ中央にあたる保木脇地区、帰雲(かえりぐも)と呼ばれる地に、戦国時代白川郷一帯から越中にかけて勢力を振るっていた内ケ島氏の居城帰雲城があった。
天正13年11月29日(1586年1月18日)深夜、突然の大地震によって、大規模な山崩れが起こり、帰雲城は城下町ともども一瞬にして崩落した土砂の地中深くに埋まった。城主内ケ島氏一族を含む領民300人はことごとく遭難し、一夜にして滅亡したと伝えられる。
出典 岐阜県ホームページ

秀吉と家康にとっての天正地震
この地震がなければ、家康は秀吉の大軍から総攻撃を受けるはずだったといわれている。秀吉は紀州や四国など版図を飛躍的に拡大し、家康との軍事力には大きな差がついていた。戦に突入すれば、家康には滅亡の可能性すらあったといわれている。
ところが震災で前線基地の大垣城が全壊焼失、秀吉軍を展開させるはずの美濃・尾張・伊勢地方の被害が大きく、戦争準備どころではなくなっていた。
家康側も岡崎城が被災していたが、領国内は震度4以下だったという。秀吉は家康征伐を中止して和解路線に転じ、家康は豊臣政権ナンバー2の座を確保し将来に備えることができたと言われている。
出典 日経BizGate

伊達政宗の震災復興策
400年後に活きた政宗の震災復興策
政宗死後の1646年に完成した奥州街道も津波被災地を避けて内陸部を通っていたことで東日本大震災時の早期の道路啓開につながった。奥州街道は遠野市や盛岡市などの津波被害の恐れが少ない内陸部の都市が発展する契機にもなった。
出典 日経BizGate

まとめにかえて
地震は豊臣秀吉から徳川家康に天下統一の流れを変えました。さらに震災復興の経験を伊達政宗は地域に生かし、その取り組みは東日本大震災でも生きていたといえます。
災害に被災しても、その後の復旧と復興を繰り返してきた歴史の上に現在があります。防災は復旧・復興の始まりともいえます。
知りたいみやぎ復興の知恵
宮城県復興・危機管理部復興支援・伝承課の公式YouTubeチャンネルです。
東日本大震災からの復興や、震災の記憶や教訓の伝承に関する情報を発信します。
出典 宮城県復興支援・伝承課
「秀吉と家康 運命を左右した2つの地震」磯田道史さんと学ぶ 災害と生きてきた日本人
歴史上、何度も大地震に襲われてきた日本列島。先人たちは災害に立ち向かい、復興も遂げてきました。戦国時代に天下統一を目指した「豊臣秀吉」と「徳川家康」。その時代に起きた2つの大きな地震、「天正地震」(1586年)と「慶長伏見地震」(1596年)。歴史学者の磯田道史さんは、「この2つの地震が二人の運命を左右し、天下の行方も大きな影響を受けた」といいます。
出典 NHK防災