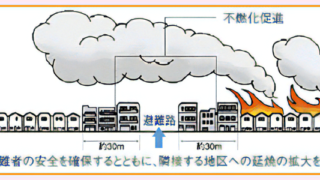台風
台風 季節外れの台風、特徴や対策を心得ておく・11月30日 平成2年台風28号
1990年、季節外れの台風である平成2年台風28号が和歌山県白浜町に上陸し、本州を縦断しました。この台風は、台風の上陸記録が始まった1951年以降で最も遅い上陸日となり、それまでの記録を1カ月以上も更新しました。台風シーズンが8月から9月である中、このような遅い時期の台風は珍しく、季節外れの台風に対する備えの重要性を改めて感じさせられます。この記事では、秋の台風の特徴や暴風に対する具体的な対策についても紹介します。