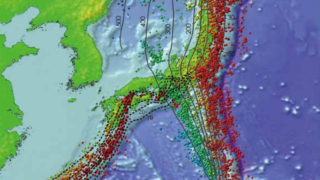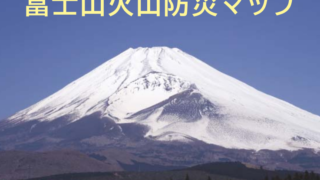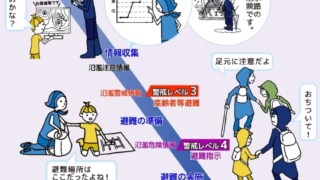つむじ風
つむじ風 気象災害としての突風について考えてみる・12月25日 羽越本線特急列車脱線転覆事故
2005年12月25日、山形県庄内町で発生した「羽越本線特急列車脱線転覆事故」では、特急列車が突風にあおられ脱線、車両が転落するという惨事が起こりました。また、台風や竜巻などによる暴風も、家屋の被害や日常生活の混乱を引き起こします。本記事では、過去の災害事例や気象現象に潜む危険性を振り返り、突風への備え方について考えます。自然の脅威に正しく備えることで、被害を最小限に抑える術を探りましょう。