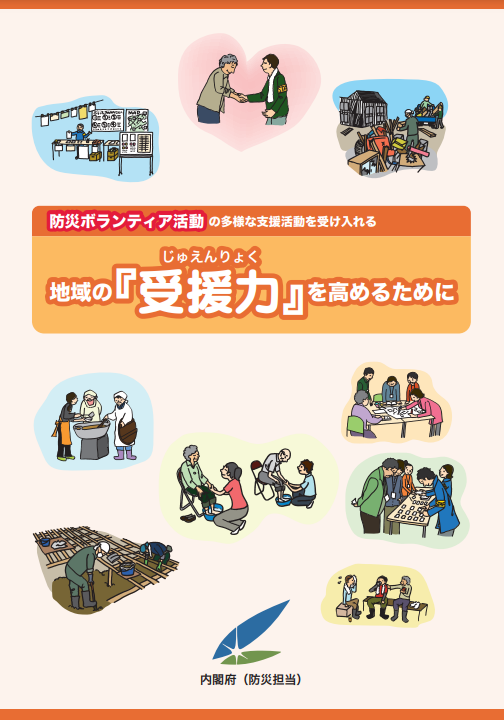1997年1月2日に発生したナホトカ号重油流出事故は、日本海沿岸の広範囲に深刻な影響を及ぼしました。この際、地元住民や全国から駆け付けた多くのボランティアが、漂着した重油の回収作業に尽力しました。この記事では、この災害を振り返りながら、ボランティア活動の意義とともに、災害時に支援を受け入れる力「受援力」の重要性について考えます。助け合いが鍵となる災害復興の現場から、地域とボランティアの連携を深めるための知恵を探ります。
重油の回収作業に多くのボランティアが参加
1997年(平成9年)1月2日 ナホトカ号重油流出事故

島根県隠岐諸島沖の日本海で、上海からカムチャツカ半島に向かっていたロシア船籍のタンカー「ナホトカ号」が大しけの中で船体が破断、分断された船体のうち船首部分が福井県三国町付近に座礁しました。
日本海で低気圧が急速に発達した後、冬型の気圧配置が強まっており、積荷の重油は北西季節風にあおられ東北から山陰にかけての日本海側の10府県の沿岸に漂着しました。悪天候もあって船首からの重油抜き取り作業は難航しましたが、その一方で沿岸に漂着した重油の回収作業に当たっては多くのボランティアが参加したことでも知られています。

ボランティアと「受援力」
ボランティアとは
ボランティアについて明確な定義を行うことは難しいが、一般的には「自発的な意志に基づき他人や社会に貢献する行為」を指してボランティア活動と言われており、活動の性格として、「自主性(主体性)」、「社会性(連帯性)」、「無償性(無給性)」等があげられる。
出典 厚生労働省|ボランティアについて
「受援力」とは
ボランティアを地域で受け入れる環境・知恵などのことを「受援力」(支援を受ける力)と言っています。ボランティア活動の多様な支援活動を受け入れるには、「受援力」を高めることが必要です。
被災地の再建には、ボランティアの支援力とともに被災地の「受援力」が欠かせないということである。この「受援力」の向上により、ボランティアの力が引き出され、被災地の復興がより迅速に進むことになる。
内閣府(防災担当)|地域の『受援力』を高めるために(刊行にあたってより抜粋) 内閣府(防災担当)地域の『受援力を高めるために』
ボランティアを受け入れる際の知恵
ボランティアを受け入れる際の知恵を紹介していきます。
「受援力」その1
平時に高める「受援力」
地域の情報の整理、ボランティアの受け入れ方法等を知っておく、お手伝いを把握しておく
●地域の情報の整理(地域の危険箇所をチェックしたり、そのマップづくりなど)をしておけば、ボランティアの受け入れの際に役立てることができます。
●地域によっては、災害ボランティアセンターを実際に設置する訓練を行っている場合があります。訓練に参加して、地域内でお互いに顔見知りになっておくこと、ボランティアの受け入れ方法やボランティアがどういう活動をするのかを知っておくのも大事です。
●災害時にお手伝いをしてもらえる相手が誰かを把握しておくことが大事です(地域の市区町村役場、社協、自治会・町内会、民生委員・児童委員など)。
災害時:お手伝いの依頼の基本
「地域の状況」を具体的に伝える、ボランティアは準備を行ってきます、パイプ役を務める、支援のお願いを災害ボランティアセンターに出す
●ボランティアにお手伝いのお願いをする際には、身の回りの状況や誰が困っているのかなど
「地域の状況」をできるだけ具体的にお伝えすることが大事です。災害の際はそのための情報
収集にも努めましょう。
●ボランティアは原則として、被災地に負担をかけないよう、水・食事・衣服・宿泊場所等の
準備を行ってきますので、食事・宿泊場所などの提供や報酬等も必要ありません。道具の貸
出し等も災害ボランティアセンターが行いますので、心配はいりません。困ったときはお互
い様なので、お手伝いしてもらいましょう。もちろん感謝の気持ちを忘れずに。
●受け入れをすることになったら、自治会・町内会、民生委員・児童委員などの地域の実情を
ご存じの地域のリーダーの人たちは、地元のボランティアとともに、パイプ役を務めて地域
に紹介するとスムーズに進みます。
●支援のお願い(=ニーズ)を、災害ボランティアセンターに出すことによって、ボランティ
アの人たちがお手伝いにきてくれます。
ニーズの出し方は、
①地域のリーダーの人たちが地域単位で取りまとめてお願いする、
②各家に配布されたチラシをみて個別にお願いする、
③ボランティアが直接訪問し、聞いてくれる
などの方法があります。

「受援力」その2
ボランティア活動の基本
ボランティアは日中に活動します、すぐに対応してもらえないこともあります、危険なところでの活動は留意する
●ボランティアは日中に活動をしますが、天候が悪いときなどは行わないことがあります。また、平日よりも土日に人数が集まりやすくなっています。
●ボランティアは自発的な活動ですので、ボランティアの人数が少ない場合などはすぐに対応してもらえないこともあります。
●ボランティアは原則として、「ボランティア保険」に加入していますが、危険なところでの活動はさせないなど地域としても留意する必要があります。

「受援力」その3
復興時のボランティアとのおつきあい
復興計画や新しいまちづくりへの参画、身近なボランティアや行政の窓口に相談、お礼のメッセージや近況を伝える、関係づくりをする
●復興計画や新しいまちづくりに、行政や地元の住民だけでなく、ボランティアも一緒に参画することにより、コミュニティが活性化し、よりよい計画づくりやまちづくりにつながります。
●暮らしの再建には、法律や都市計画、建築などの専門知識が必要になる場合があります。専門家がボランティアとして被災地の再建を支援している例があります。まずは、身近なボランティアや行政の窓口に相談すれば、解決策やヒントが見つかるかもしれません。
●避難所での暮らしでお世話になったり、家屋の片付けなどを手伝ってもらったボランティアに、手紙などでお礼のメッセージや近況をお伝えしましょう。関わったボランティアの人たちにとっても嬉しいものです。
●災害時に出会ったボランティアが、被災した地域のファンやリピーターになってもらえるように関係づくりをしておくことが大切です。

受援力を身につける
KYジャーナル 〝受援力〟を身につけよう
あえて空気は読まず、ズバッと解説、山本恵子(Keiko Yamamoto)のKYジャーナル。
今回のテーマは「助けて」「手伝って」と言える力、〝受援力〟です。
出典 NHK名古屋放送局
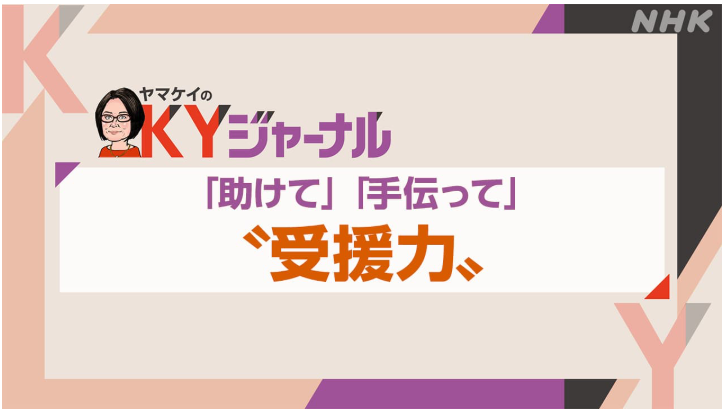
まとめ
「受援力」とは、被災地となった際にボランティアを地域で受け入れるための環境や知恵など、「支援を受ける力」をさします。
被災者にボランティア活動がよく理解されていない、また、外部の見知らぬ人から支援を受けることへの警戒心からボランティアの受け入れを拒否してしまうなど、ボランティアが十分に力を発揮できない事例があります。助けが必要な時は「助けてください」と言うことが必要です。そして誰に助けを求めるかを、事前に考えておくことが「受援力」を高める上で大事になります。